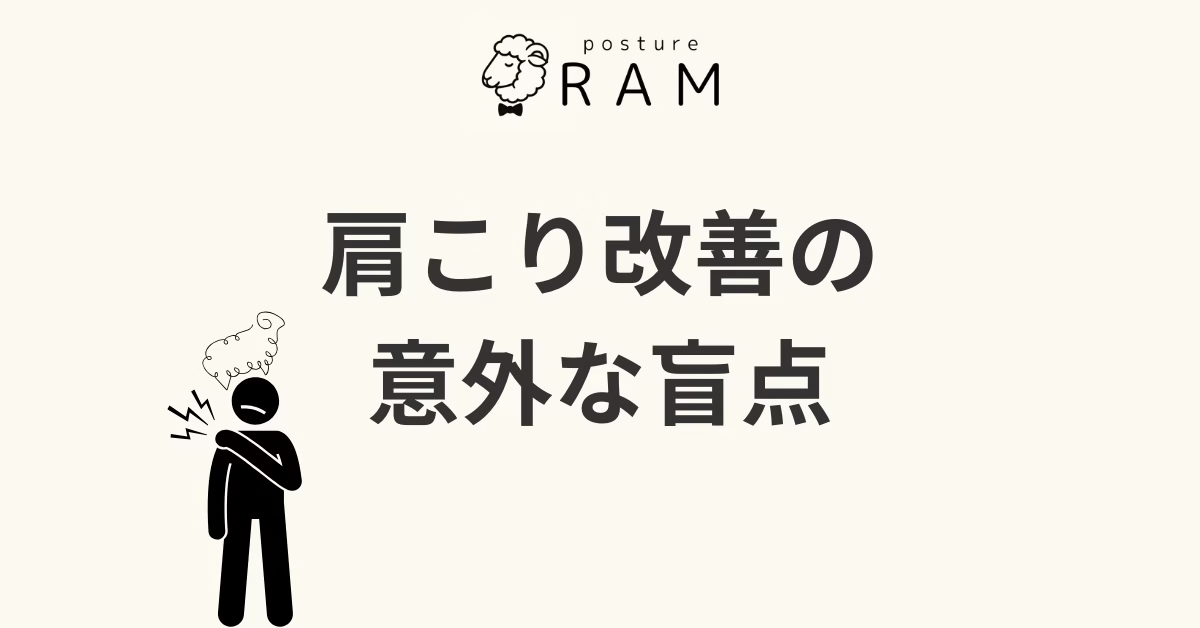つらい肩こりの解消法として人気の「肩甲骨はがし」、あなたも試したことはありますか?
でも、もし良かれと思って続けているそのケアが、かえって肩こりを悪化させているとしたら…?
この記事では、肩甲骨はがしに潜む意外な落とし穴と、その効果を最大限に引き出すための「正しい体の使い方」を専門家の視点から解説します。
今までとは違う、スッキリ軽い肩を目指していきましょう。
あなたの肩甲骨はがしは大丈夫?よくある危険性と「見過ごされがちな落とし穴」
そもそも「肩甲骨はがし」って何?
「肩甲骨はがし」という言葉、よく聞きますよね。
これは、肩甲骨と背骨や肋骨との間に張り付くように硬くなった筋肉をほぐし、まるで「剥がす」かのように肩甲骨の動きをスムーズにする手技やセルフケアの総称です。
肩甲骨が本来の動きを取り戻すことで、肩こりや姿勢の改善が期待できると言われています。
セルフケアでやりがちな3つの危険
肩甲骨はがしを自分で行うとき、ついやってしまいがちな注意点があります。
まずは、基本的なリスクから確認しておきましょう。
強すぎる力でのゴリゴリはNG!
「痛いほど効くはず」と、強い力でゴリゴリとマッサージしていませんか?
強すぎる刺激は、筋肉の繊維や周りの組織を傷つけてしまう「揉み返し」の原因になります。
気持ちいいと感じる、優しい力加減を心がけてくださいね。
痛みを我慢して動かすのは逆効果
ストレッチ中に痛みを感じたら、それは「それ以上は伸ばさないで」という体からのサインです。
痛みを我慢して無理に動かすと、筋肉が防御反応でこわばり、かえって硬くなってしまいます。
「痛気持ちいい」の範囲で、ゆっくりと行いましょう。
持病がある方や妊娠中の方は要注意
血圧に問題がある、骨がもろくなっている、または妊娠中など、体の状態によってはマッサージやストレッチが負担になることがあります。
体に不安がある方は、自己判断で行わず、必ずかかりつけの医師や専門家に相談してください。
【ここが重要】良かれと思って…可動域アップが招く「間違った動きのクセ」という落とし穴
一般的な注意点に加えて、実はもっと見過ごされがちな「落とし穴」があります。
私の臨床経験上、良かれと思ってケアを頑張った結果、無意識に「間違った動きのクセ」がついてしまっている方が少なくありません。
解説!「肩をすくめて腕を上げる」クセがついていませんか?
腕を上げるとき、肩まで一緒にグイっと持ち上げてしまう動き、心当たりはありませんか?
これが、いわゆる「肩をすくめる」クセで、多くの方に見られる傾向があります。
肩甲骨はがしで可動域が広がると、この動きがより大きくなりやすく、首や肩の筋肉に余計な力が入ってしまうのです。
なぜ?動きやすくなったのに、かえって肩こりがひどくなる理由
肩をすくめるクセがあると、常に首から肩にかけての筋肉が緊張した状態になりがちです。
本来、腕を上げる際には肩甲骨と腕の骨が「肩甲上腕リズム」という決まった割合で連動して動きますが、このリズムが崩れると、特定の筋肉にばかり負担がかかってしまうのです。
これが、ケアしているのに改善しにくい理由の一つと考えられます。
もったいない!肩甲骨はがしの効果をムダにしない「正しい体の使い方」
せっかくのケアをムダにしないために、肩甲骨の「正しい動かし方」を身につけましょう。
目指すのは、肩の力を抜いて、腕をスムーズに動かせる状態です。
目指すのは「肩を下げたまま腕を動かす」感覚
大切なポイントは、肩甲骨を意識的に「下げる」ことです。
肩の位置を安定させたまま、腕だけを動かす意識を持つことで、首や肩への余計な負担を減らすことができます。
この感覚を覚えることが、根本的な肩こり改善への第一歩になります。
あなたのクセはどっち?今すぐできる簡単セルフチェック
鏡の前に立ち、リラックスした状態でゆっくりと腕を真横から45°~60°くらい上げてみましょう。
- 良い例: 肩の位置はあまり変わらず、腕だけがスムーズに上がっていく。
- 注意したい例: 腕を上げ始めると同時に、肩が耳の方に近づいていく。
もし肩が上がってしまう方は、「肩をすくめる」クセがついているかもしれません。

今日からできる!正しい動きを体に覚えさせる2ステップ練習法
正しい動きの感覚を体に覚えさせる、簡単な練習法をご紹介します。
この練習は、肩の無駄な力みをリセットし、肩甲骨と腕を分離して動かす感覚を養うことが目的です。
ステップ1:まずは肩甲骨を「下げる」練習から
- 両肩を耳に近づけるように、ぐっとすくめます。
- そこから一気に力を抜き、ストンと肩を落とします。
- 最後に、その落ちた位置からさらに1cmだけ肩甲骨を「下げる」意識をします。
この「下がった位置」が、あなたの肩の基本ポジションです。
ステップ2:「下げたまま」ゆっくり腕を動かしてみよう
- ステップ1で確認した「下がった位置」をキープします。
- その状態のまま、腕の重みを感じながら、ゆっくりと腕を前に持ち上げていきます。
- 肩が一緒に上がってこないように意識しながら、上がるところまでで止め、ゆっくり下ろします。
この練習で、肩甲骨と腕の動きを分離させる感覚を養いましょう。
肩を下げる動きがどうしても難しい方は、キャットアンドカウで背骨を柔らかくしましょう。
▶キャット&カウで良い姿勢を作る?背骨と腹筋の連動トレーニング
これでもう迷わない!セルフケアと専門家選びのポイント
正しい体の使い方を意識しながら、安全なセルフケアや専門家選びを行いましょう。
自分でやるならコレ!安全にできるおすすめストレッチ
- 椅子に浅く座り、背筋を伸ばします。
- 両手を背中の後ろで組みます。
- 肩甲骨を「下げる」意識をしながら、組んだ手をゆっくりと後ろに引いて胸を開きます。
- 気持ちよく伸びるところで、20秒ほど深呼吸をしながらキープします。
ポイントは、肩をすくめず、あくまでも胸を開く意識で行うことです。
後ろに上げると肩も一緒に上がってしまうので注意してください。
専門家にお願いするときのチェックリスト
もし整体やマッサージなど、専門家にお願いする場合は、以下の点を確認してみましょう。
- ただ強く揉んだり、無理に動かしたりするだけではないか?
- 施術後の体の変化を確認してくれるか?
- 今回お伝えしたような、日常での「正しい体の使い方」についてもアドバイスをくれるか?
良い専門家は、あなたの体のクセを見抜き、根本的な改善に向けたサポートをしてくれるはずです。
まとめ
肩甲骨はがしは、肩こりで悩む方にとって、即効性のあるとても良い施術・セルフケア方法です。
しかし、だからこそ注意も必要です。
- 肩甲骨はがしの落とし穴
可動域が広がることにより、「肩をすくめる」といった間違った動きのクセがつきやすくなります。 - 正しい体の使い方
大切なのは、肩甲骨を「下げた」状態で腕を動かす意識を持つことです。 - ケアはセットで考える
ほぐすこと(はがすこと)と、正しく動かすことは、必ずセットで行いましょう。
肩甲骨はがしそのものが悪いわけではありません。
大切なのは、動きやすくなった体をどう使うか、という視点です。
ぜひ今日から肩甲骨はがしに「肩を下げる」意識をプラスして、肩甲骨はがしの効果を最大化しましょう。
関連記事
肩こりの原因についてまとめています。
▶肩こりの本当の原因は一つじゃない!肩こりの原因まとめ
悪い姿勢の種類をしって、他の自分のクセを見つけましょう。
▶あなたはどのタイプ?悪い姿勢の種類を徹底解説!
良い姿勢になれるようにすると、いろいろな身体のクセを改善することができます。
▶その姿勢改善、逆効果かも?理想の「ゴールデンライン」とは
柔道整復師/姿勢改善パーソナルトレーナー
さいたま柔整専門学校卒業。
三郷市内グループ接骨院で院長を歴任。
現在、「姿勢改善Studio きずな日暮里」を運営中。