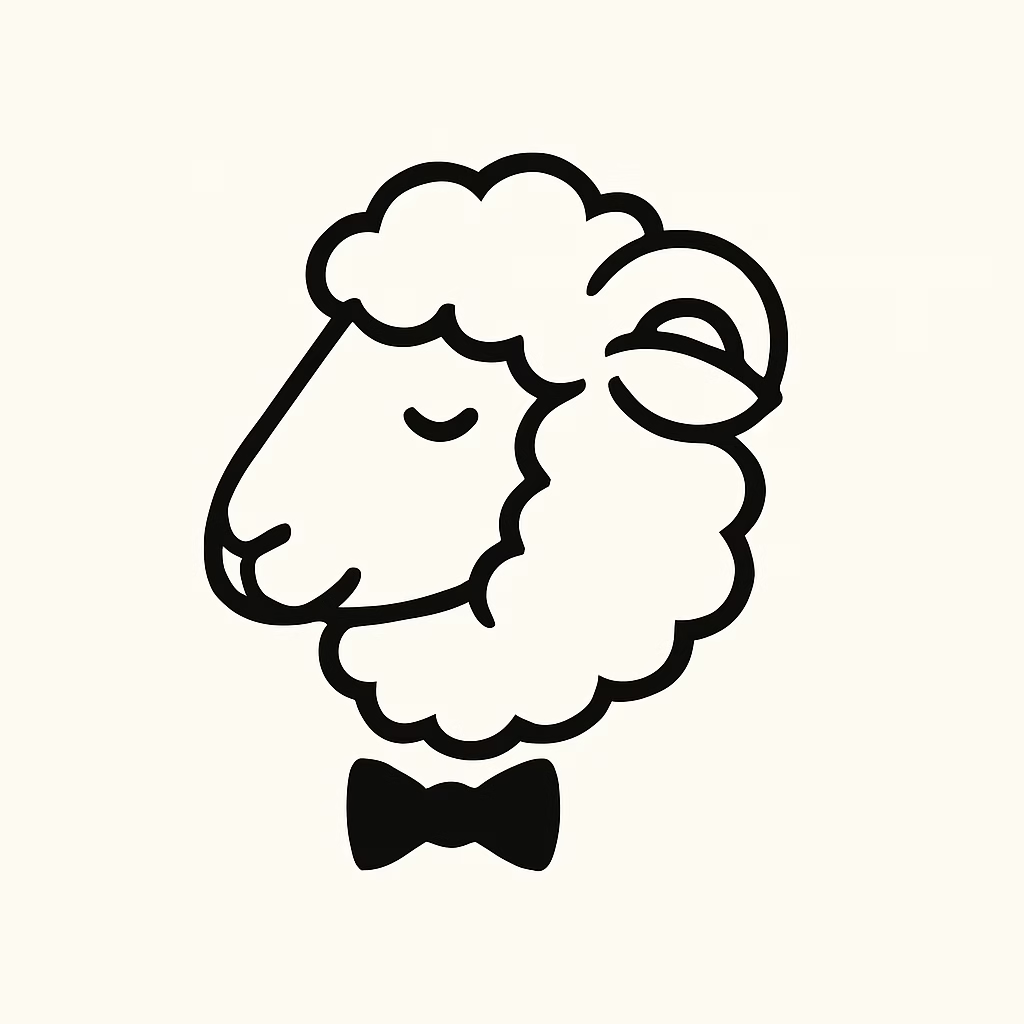肩こりがなかなか良くならない。
ストレッチやトレーニングをしても、すぐに戻ってしまう。
もしかすると、その原因は「僧帽筋」の使い方にあるかもしれません。
この記事では、僧帽筋の基本構造から肩こりや姿勢との関係、改善のヒントまでをわかりやすく解説します。
僧帽筋とは?3つの部位とその役割
僧帽筋はどこにある?基本構造と位置関係
僧帽筋は、首の付け根から背中の中央あたりまで広がる大きな筋肉です。
肩甲骨や背骨に付着しており、形が“僧帽子”に似ていることから名付けられました。
首から肩、背中の上部まで覆っているため、肩こりや姿勢と密接に関係しています。
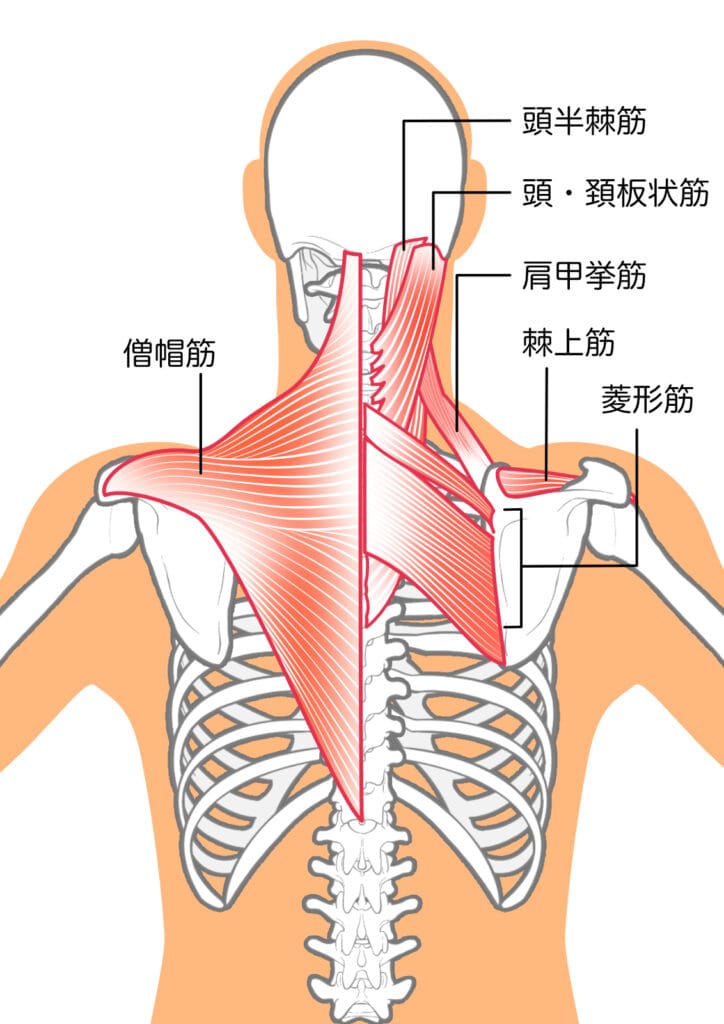
上部・中部・下部それぞれの役割と動き
僧帽筋は「上部」「中部」「下部」に分けて考えると理解しやすくなります。
- 上部僧帽筋:肩をすくめる動作を担当
- 中部僧帽筋:肩甲骨を内側に寄せる
- 下部僧帽筋:肩甲骨を下に引き下げる
この3つの働きがバランス良く使えていないと、肩こりや巻き肩、猫背などに繋がることがあります。
よくある誤解「僧帽筋=肩をすくめる筋肉?」
僧帽筋というと「肩を上げる筋肉」という印象が強いかもしれません。
これは上部僧帽筋の働きだけを切り取った認識です。
実際には、中部・下部の働きが重要で、むしろ上部ばかりが働く状態が続くと不調の原因になります。
僧帽筋と肩こり・巻き肩の意外な関係
上部僧帽筋ばかり使うとどうなる?
上部僧帽筋は、緊張しやすい筋肉です。
とくにデスクワークやスマホの操作中、「肩をすくめるような姿勢」が無意識に続くと、過剰に使われてしまいます。
これがいわゆる“肩こり”の正体。
「肩が上がった状態」が癖になると、呼吸も浅くなりがちです。
「肩甲骨を寄せる」だけでは巻き肩は治らない?
姿勢をよくしようとして「肩甲骨を寄せる意識」を持つ方は多いですが、
このときに中部僧帽筋だけでなく上部まで使ってしまうと、肩がすくんでしまい逆効果になることがあります。
巻き肩の改善には「肩を下げてから寄せる」動きが必要です。
つまり、下部僧帽筋を同時に働かせることがカギになります。
下部僧帽筋が働くと姿勢が安定する理由
下部僧帽筋は、肩甲骨を下げて支える役割を担っています。
ここがしっかり使えると、自然と肩の力が抜けやすくなります。
肩が下がることで、肩甲骨が安定し、上部僧帽筋の過緊張もやわらぎます。
結果として、肩こりや巻き肩の緩和に繋がるのです。
僧帽筋を整えるための意識とアプローチ
日常生活で僧帽筋に負担をかけないコツ
- 肩をすくめない姿勢を意識する
- 画面を見るときは目線を下げすぎない
- 肩で物を持つ・支えるクセを減らす
こういった小さな工夫が、僧帽筋への負担軽減に繋がります。
下部僧帽筋の活性化で「肩を下げる」意識を育てる
下部僧帽筋は、意識しづらく動かしにくい部位です。
そのため、地道なトレーニングが必要です。
おすすめのエクササイズ:壁スクラップ(壁に背をつけた肩甲骨下制)
- 壁に背中・頭・骨盤をつけて立つ
- 肘を曲げた状態で肩を下げ、壁に肘を軽く押しつける
- 肩が上がらないよう注意しながら、肩甲骨を下に引く意識で10秒キープ
これを1日数回くり返すだけでも、下部僧帽筋を使う感覚が育っていきます。
トレーニングやストレッチで意識したいポイント
上部僧帽筋の過緊張をゆるめるストレッチ
①デスクワークやスマホでこりやすい上部僧帽筋は、まず“ゆるめる”ことが大切です。
やり方(左右どちらも行う)
- イスに座り、片方の手で座面を軽くつかむ
- 反対の手を頭の横に添え、ゆっくり斜め前へ倒す
- 首の横〜肩のラインに伸び感が出たらそのまま20秒キープ
注意点
- 肩がすくまないように意識する
- 反動をつけない
ストレッチ後は、肩まわりがスッと軽くなる感覚が得られやすくなります。
中部・下部僧帽筋の筋肉に刺激を入れるトレーニング
②姿勢改善には「支える力」が必要です。
とくに下部僧帽筋は意識しづらく、鍛えるのにコツがいります。
おすすめ種目:うつ伏せ Yエクササイズ
- うつ伏せで寝て、両手をYの字に広げる(親指を天井へ向ける)
※肩があがらないように注意! - おでこを床につけたまま、肘を伸ばした状態で腕を少し浮かせる
- 肩甲骨を下げる意識で10秒キープ × 3セット
ポイント
- 腰を反らせないように注意
- 腕より肩甲骨の動きを重視する
動作は小さくてOK。地味な動きでも、しっかり筋肉に入る種目です。
意識する順番:ゆるめる → 動かす → 支える
③筋肉を正しく使えるようになるには、順番が大事です。
- まず「硬くなっている筋肉」をゆるめる(例:上部僧帽筋)
- 次に「本来使うべき筋肉」を動かす(例:中部・下部僧帽筋)
- 最後に「姿勢保持として使えるか」を確認する
この順番を飛ばすと、結果的にまた肩に力が入り、同じ不調を繰り返すことになります。
無理に「正しい姿勢」を保とうとせず、少しずつ筋肉を使えるようにしていくのがコツ
姿勢は「がんばって保つもの」ではなく、「自然と支えられる状態」に近づけていくのが理想です。
無意識でも安定したフォームを保つためには、まず意識的な練習が必要です。
徐々に意識と使い方が一致してくると、姿勢も自然に整いやすくなります。
▶骨の軸で支える良い姿勢とは?メリット・チェック・トレーニングまとめ
まとめ
- 僧帽筋は「上部・中部・下部」に分かれており、それぞれ役割が異なる
- 上部ばかりが働くと肩こりや巻き肩を引き起こしやすい
- 姿勢改善には、下部僧帽筋を使って「肩を下げる」意識が重要
僧帽筋は肩まわりの姿勢・動きの中心にある筋肉です。
使い方のクセを見直し、バランスよく働かせることで、慢性的な不調も軽減できます。
日々の生活に小さな意識を取り入れることから始めてみましょう。
筋トレで効かせるコツの解説はこちら
▶筋トレが効かない?感覚がわからない原因と「効かせるコツ」完全解説
クセを見直すヒントはこちら
▶症状や姿勢がすぐ戻る理由とは?使いやすい筋肉と使いにくい筋肉の違い